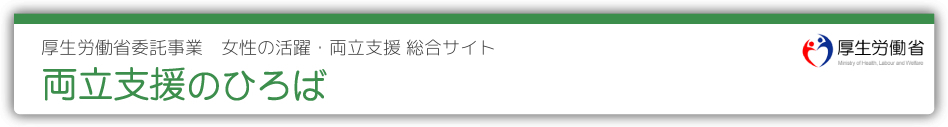両立指標の配点についての考え方
【分野1】両立支援のための環境整備
- ◇1-1(方針の明文化)は、経営トップが取組の必要性を十分に理解し、その決断の下に実施していくことは、取組の最も基礎たる部分であり、10点とした。
- ◇1-2(管理職への徹底)、1-3(制度利用の働きかけ)、1-4(従業員の意見等の取り上げ)、1-5(従業員代表等との話合い)、1-7(年次有給休暇の取得促進)、1-9(ノー残業デーなど所定外労働削減のための措置)、1-16(急な不在への対応)、1-26(介護に関する実態把握)、1-27(育児と仕事の両立についての情報交換のサポート)及び1-28(介護と仕事との両立についての情報提供・研修等)は、企業のとり得る措置に裁量性があるため、5点とした。
- ◇1-6(年次有給休暇の弾力的な制度化)、1-8(年次有給休暇の取得率)、1-10(フルタイム労働者1人あたりの法定労働時間及び法定休日労働の時間数が各月毎に45時間未満であること及び法定時間外労働時間が60時間未満の労働者の有無)は、仕事と家庭における両立支援の取組を進めるためには、業務の改善による効率的な働き方の実現も同時に行う必要があることから、WLBの整備状況として重要である。1-6については、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、有効活用を目的として、時間単位取得できることとしたものであり、効果的な取組であることから、10点とした。1-8、1-10については、WLBの整備状況の実態を数字という客観的要素で確認できる取組であって、取組の効果を定量的に把握することが可能で、進行管理がしやすく、実効的な両立支援となり得るため、1-8については10点、さらに、1-10については労働時間削減のための取組に関する設問であり、労働者の福祉及びWLBの推進に欠かせないものであるため15点とした。
- ◇1-11(多様な休暇制度)、1-12(育児・介護目的以外の両立支援制度)、1-14(テレワーク制度)は、育児・介護に限定しない企業のWLBの整備状況を判断できる指標であり、企業風土を測る問として重要な問であり10点とした。
- ◇1-13(勤務時間や勤務地等についての希望を聞く制度)は、制度のみでは両立可能な取組としては十分とはいえないため、5点とした。
- ◇1-15(代替要員の確保)は、育児・介護休業及び短時間勤務制度の利用環境整備という観点から重要であり、10点とした。
- ◇1-17(原職復帰の原則)、1-18(休業に伴う教育訓練)及び1-19(休業中の情報提供)は、育児・介護休業及び短時間勤務制度の利用終了後の就業継続を円滑に行うために重要であり、10点とした。
- ◇1-20(中・長期的なキャリア形成)、1-25(女性の平均勤続年数の推移)は、両立支援の取組を行っても、他の要素による制約もあることから、5点とした。
- ◇1-21(再雇用の制度等)は、育児・介護を自ら行いたいという意思を持つ従業員にとって復帰の手段である再雇用の制度や慣行等があることは重要であり、制度がある場合は10点、制度はないが慣行がある場合は5点とした。
- ◇1-22(育児や介護を理由とした退職者の減少)は、育児・介護を自ら行いたいという従業員も存在することから、5点とした。
- ◇1-23(育児休業利用からの復職者の退職割合)、1-24(介護休業利用からの復職者の退職割合)は、継続就業意欲のある従業員にとって、育児・介護休業の利用終了後の就業継続を円滑に行う種々の取組により減じることができるものであり、その実態を数字という客観的要素で確認できる取組であって、取組の効果を定量的に把握することが可能で、進行管理がしやすく、実効的な両立支援となり得るため、10点とした。
【分野2】仕事と育児の両立支援 制度整備状況
- ◇2-1~8は、法律上整備義務のある制度について、法律を超える内容の制度を整備したものであり、企業の自主的な取組を評価して、各10点。
- ◇2-9~12は、法律上の義務のない制度を整備したものであり、企業の自主的な取組を評価して、各10点。
【分野3】仕事と育児の両立支援 利用状況
制度が実際に利用されているかどうかを計る問は、いずれも重要であり、基本的には全て10点であるが、以下については5点加点した。
- ◇3-1(女性の育児休業利用者の割合)、3-2(男性の育児休業利用者の割合)は、特に、育児休業利用率に関する実態を数字という客観的要素で確認する問であることから、15点。
- ◇3-8(育児の経済的援助)は、制度と利用の両方についての問であることから15点(制度か利用かどちらかがあれば10点となり、他の設問とバランスがとれている)。
【分野4】仕事と介護の両立支援 制度整備状況
- ◇4-1~4は、法律上整備義務のある制度について、法律を超える内容の制度を整備したものであり、企業の自主的な取組を評価して、各10点。
- ◇4-5(介護のための所定労働時間の短縮等の措置)は、法律上、選択的措置義務(いずれかの制度を措置しなければならない義務)が課されているので、2つ以上の制度を整備した場合は、法律上の義務を上回って制度を整備したこととなるため、企業の自主的な取組を評価して、2制度目から1制度ごとに5点加算。
【分野5】仕事と介護の両立支援 利用状況
制度が実際に利用されているかどうかを計る問は、いずれも重要であり、基本的には全て10点とした。
- ◇5-8(介護についての法律上義務を果たしたことにならない一般的な経済的援助)は、制度と利用の両方についての問である。育児についての経済的援助の問(3-8)とのバランス上15点とすべきところ、育児についての経済的援助の問が1問であるのに対し、介護についての経済的援助の問は、直接に介護するサービスに係る費用が選択的措置義務となっている関係で3問(4-5(4)、5-7、5-8)に分れており、介護の3問の合算点数が育児1問の点数より高くなるため、10点。