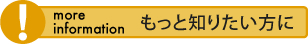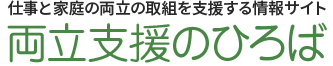- >ホーム
- >事業主の方々へのお役立ち情報
- >Q36「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」、「トライくるみん認定」、「プラス認定」を取得したい

 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、行動計画に定めた目標を達成するなどの、一定の基準を満たした場合は、必要書類を添えて申請を行うことにより「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定・トライくるみん認定)を受けることができます。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、行動計画に定めた目標を達成するなどの、一定の基準を満たした場合は、必要書類を添えて申請を行うことにより「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定・トライくるみん認定)を受けることができます。
さらに、くるみん認定・トライくるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の基準を満たした場合に特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
認定、特例認定を受けた企業は、それぞれ「認定マーク(愛称:くるみん、トライくるみん)」、「特例認定マーク(愛称:プラチナくるみん)」を、商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをPRできます。
また、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定の基準を満たした上で、不妊治療のための休暇制度、その他不妊治療と仕事との両立のための支援制度の整備等の一定の基準を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことにより、「子育てサポート企業」だけでなく「不妊治療と仕事との両立支援サポート企業」としても、厚生労働大臣の認定(くるみんプラス認定、トライくるみんプラス認定、プラチナくるみんプラス認定)を受けることができます。
令和7年4月1日から、行動計画の策定又は変更を行う際には、育児休業等の取得状況、労働時間の状況を把握するとともに、育児休業等の取得状況や労働時間の状況に係る数値目標の設定が義務付けられました(常時雇用労働者が100人以下の企業は努力義務)。
また、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準等も改正され、くるみんマーク・トライくるみんマークが新しくなりました!



くるみん認定を受けるためには、行動計画の計画期間が終了し、以下の9の認定基準のすべてを満たす必要があります。
- ①行動計画策定指針に照らし、適切な行動計画を策定したこと
- ②計画期間が2年以上5年以下であること
- ③策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
- ④策定・変更した行動計画について、公表、従業員への周知を適切に行っていること
- ⑤次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること(注1)
(1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が30%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること
(2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて50%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること - ⑥計画期間内の女性労働者及び育児休業等の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞれ75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること(注1)
- ⑦計画期間の終了日の属する事業年度において、次の(1)又は(2)を満たすこと、かつ(3)を満たすこと
(1)フルタイムの労働者(注2)の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること
(2)フルタイムの労働者のうち、25歳~39歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
(3)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと - ⑧男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置、年次有給休暇の取得の促進のための措置、短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置のいずれかについて成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
- ⑨法及び法に基づく命令その他関係法令(労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パート・有期雇用労働法、女性活躍推進法、労働施策総合推進法など)に違反する重大な事実がないこと
<プラチナくるみん認定>
認定を受けるためには、行動計画の計画期間が終了し、以下の11の認定基準のすべてを満たす必要があります。
- ①行動計画策定指針に照らし、適切な行動計画を策定したこと
- ②行動計画期間が2年以上5年以下であること
- ③行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
- ④策定・変更した行動計画について、公表、従業員への周知を適切に行っていること
- ⑤次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること
(1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が50%以上であること
(2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて70%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること(注1) - ⑥計画期間内の女性労働者及び育児休業等の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること(注1)
- ⑦計画期間の終了日の属する事業年度において、次の(1)又は(2)を満たすこと、かつ、(3)を満たすこと
(1)フルタイムの労働者等(注2)の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること
(2)フルタイム労働者のうち、25歳~39歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
(3)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと - ⑧次の(1)~(3)のすべての措置を実施しており、かつ、(1)又は(2)のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと
(1)男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 - ⑨次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用している者を含む)している者の割合が90%以上であること
(2)子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること(注1) - ⑩育児休業等をし、又は育児を行う男女労働者が、職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること
- ⑪法に基づく命令やその他関係法令(労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パート・有期雇用労働法、女性活躍推進法、労働施策総合推進法など)に違反する重大な事実がないこと
●プラチナくるみん認定(プラチナくるみんプラス認定を含む)を取得した企業は、その後の行動計画の策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年少なくとも1回、公表日の前事業年度(事業年度=各企業における会計年度)の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。
・1回目の公表は、プラチナくるみん取得後おおむね3か月以内
・2回目の公表は、公表事業年度終了後おおむね3か月以内
に行ってください。
<トライくるみん認定>
認定を受けるためには、行動計画の計画期間が終了し、以下の9の認定基準のすべての条件を満たす必要があります。
- ①行動計画策定指針に照らし、適切な行動計画を策定したこと
- ②行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること
- ③策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
- ④策定・変更した行動計画について、公表、従業員への周知を適切に行っていること
- ⑤次の(1)又は(2)のいずれかを満たしていること(注1)
(1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が10%以上であること
(2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて20%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること - ⑥計画期間内の女性労働者及び育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞれ75%以上であること(注1)
- ⑦計画期間の終了日の属する事業年度において、次の(1)及び(2)を満たすこと
(1)フルタイムの労働者(注2)の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと - ⑧男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置、年次有給休暇の取得の促進のための措置、短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置のいずれかについて具体的な目標を定めて実施していること
- ⑨法に基づく命令やその他関係法令(労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パート・有期雇用労働法、女性活躍推進法、労働施策総合推進法など)に違反する重大な事実がないこと
<プラス認定>
認定を受けるためには、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの認定基準を満たしていること(あるいは既に認定を受けていること)に加えて、以下の認定基準のすべてを満たす必要があります。
- (1)次の①及び②の制度を設けていること
①不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用できる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を含みません。)
②不妊治療のために利用可能な半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務等のうちいずれかの制度 - (2)不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている社内制度の内容とともに社内に周知していること
- (3)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること
- (4)不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる両立支援担当者を選任し、社内に周知していること
(注1)従業員数が300人以下の事業主の場合、特例が認められています。
(注2)「フルタイムの労働者」とは短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律2条第1項に規定する短時間労働者を除く、全ての労働者をいいます。